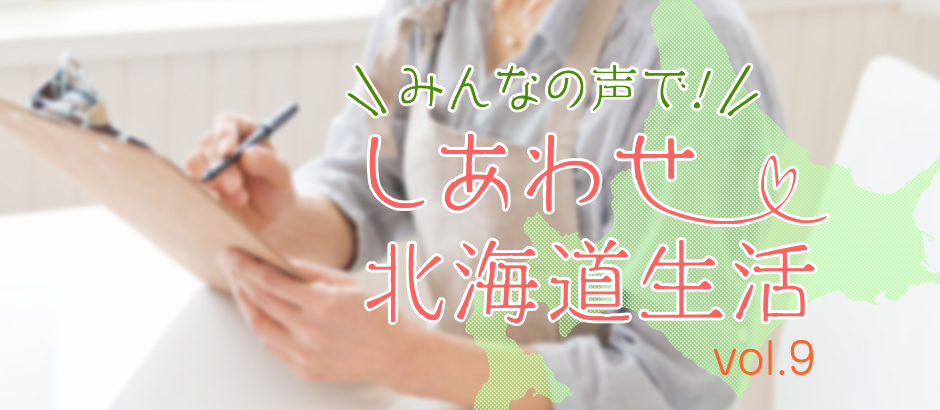お金の勉強 その1「老後の生活資金について」
みんなの声で!しあわせ北海道生活 vol.9
こちらに掲載されている記事の、ポイント獲得・抽選応募期限は終了しております。
そろそろボーナス!という方も多いのでは?
「もうボーナス払いで行き先は決まっている・・」「そもそもボーナスは出ない・・・」など
切ない声が聞こえてきそうですが、6月はお金についてのエネモール会員のみなさんの不安をお金のプロにお答えいただきます!
アンケート結果発表
「貯蓄に関する心配事」について、エネモール会員のみなさんにお答えいただいた、トップ5の発表です。
| 1位 | 老後の生活資金 | 78.9% |
|---|---|---|
| 2位 | 病気や不時の災害への備え | 57.2% |
| 3位 | 旅行、レジャーの資金 | 32.5% |
| 4位 | 車や家電製品などの耐久消費財の購入資金 | 30.7% |
| 5位 | こどもの教育資金 | 20.0% |
(複数回答)
今回から3週にわたってファイナンシャルプランナーの川部紀子さんにお金の不安に関する対処法や心得を教えていただきます。
今回は約8割の方が不安に思っている「老後の生活資金」についてお話しいただきます。

川部紀子さん
人生100年時代、日本人最大の心配事は「老後の生活資金」かもしれません。
その現れでしょう、「年金不安」、「老後破たん」といった言葉があちこちで飛び交っています。
実際のところ、厚労省発表の夫婦の標準的な年金額(2018年度)は月換算で約22万円です。これに対し、総務省が今年発表した60代夫婦の1か月の消費支出は約29万円です。貯蓄を取り崩して暮らしている夫婦が日本中にいることが想像できます。今後、年金は減り、増税や物価上昇が考えられますので、さらに状況は悪化していくでしょう。

対策を考える前に、まず行いたいのが退職金と親の資産を確認することです。真面目な人ほど、これらに期待しない自分を良しと考えている節がありますが、そうは思いません。
「有り」の場合、数百万~数千万円もの金額になりますので、人生設計の計算に入れないのは、雑な見積もりです。この確認で、過度の不安や節約から解放される人はかなりいます。これらの人は、ぜひとも、消費を引っ張って、経済を活性化させていく側に回ってほしいものです。
「無し」が確認できた場合は本腰を入れましょう。退職金や親の資産「有り」の人たちと同じ暮らしをしていては、60歳過ぎて貯蓄額に大きな差を付けられてしまいます。「有り」の方々は、自身でも貯めていたりする傾向があるので、老後格差は大きく広がると思われます。
老後資金を自力で作っていくためにもっとも合理的な方法は「確定拠出年金」だと考えています。職場で「企業型 確定拠出年金」を導入している場合は、前向きに活用しましょう。自分のお金を上乗せして積み立てできるマッチング拠出が可能な職場ならぜひ検討すべきです。
職場に導入されていない方は「iDeCo(イデコ)」と呼ばれる「個人型 確定拠出年金」を検討しましょう。
「確定拠出年金」は、60歳前には換金できない制度ですから、老後の資金作りにはピッタリです。

「イデコちゃん」
こういった話になると必ず「そんなに生きない」という人がいます。いえいえ、そんな人に限って長生きするものですよね。
インタビュー後記
川部さんのお話を聞いて、寿命が年々伸びているので本当に100年で計画しなければならないと痛感しました。
おすすめの「iDeCo(イデコ)」に関するお話は4週目に詳しくお伝えします!
「iDeCo(イデコ)」公式サイト https://www.ideco-koushiki.jp/
川部紀子さんプロフィール
ファイナンシャルプランナー(CFP®1級FP技能士)、社会保険労務士。
生死とお金に翻弄される20代を過ごし、生きるためのお金と知識の必要性を痛感し、30歳で起業。現在「FP・社労士事務所 川部商店」代表として、個人レクチャー、講演の受講者は3万人超。テレビ・ラジオ・ネット等のメディア出演多数、著書「家計簿不要!お金がめぐる財布の使い方」等
HBC「今日ドキッ!」、AIR-G’「Sparkle Sparkler」出演中
新刊「まだ間に合う 老後資金4000万円をつくる!お金の貯め方・増やし方」(明日香出版社)を7月中旬に発売予定
ブログ「FPの胃袋」、ホームぺージ http://www.kawabe.jimusho.jp/
次回は「病気や不時の災害の蓄え」についてです。お楽しみに!
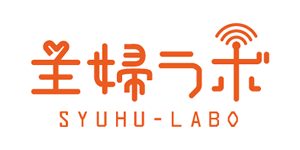
企画:主婦ラボ事務局
「主婦ラボ」は株式会社エルアイズが運営する北海道の女性の情報交換&モニターサイト。
商品や店舗のモニター会員募集中!
http://syuhu-labo.net