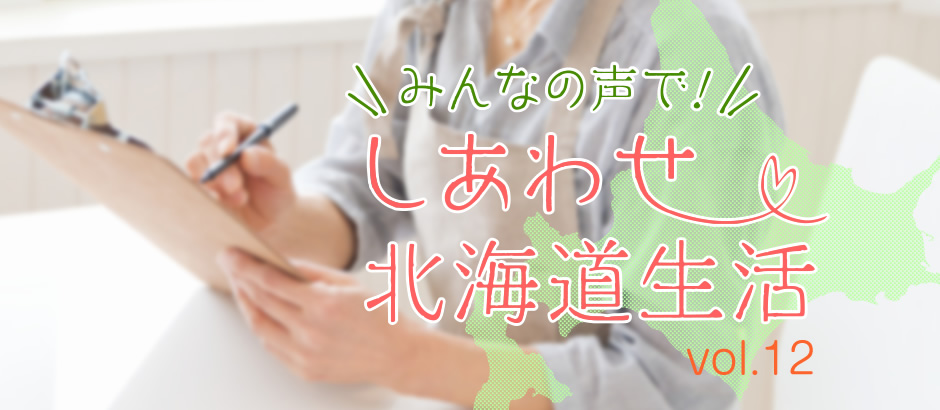お金の勉強 その4 「老後のための貯蓄法について」
みんなの声で!しあわせ北海道生活 vol.12
こちらに掲載されている記事の、ポイント獲得・抽選応募期限は終了しております。
これまで3週にわたってファイナンシャルプランナーの川部紀子さんにお金に関するお話を伺いましたが、今回は今年1月に札幌、北海、小樽の3つの信用金庫が合併した北海道信用金庫さんに貯蓄に関する心配事について解決策をお答えいただきました。

執行役員 業務企画部長 松本 健さん
業務企画部 部長代理 大矢 浩太郎さん
業務企画部 部長代理 村田 優子さん
Q:アンケートにお答えいただいた会員のみなさんの約8割もの方が不安に感じている「老後の生活資金」に関してなのですが、北海道信用金庫さんでオススメしている商品はありますか?
iDeCo(イデコ)と言われる「個人型確定拠出年金」制度を活用すると良いのではないでしょうか。「年金」とついている通り、老後の生活資金を補うためにはもってこいの商品です。また、税金が軽減されるのも魅力です。
掛け金は全額所得控除されますし、運用で得た利益は非課税となります。

「イデコちゃん」
Q:どなたでも加入できるのですか?
昨年から加入できる方の条件が広がって20歳から60歳未満の方のほぼすべての方が加入できるようになりました。
Q:北海道信用金庫さんでは加入ができるのですか?
ご加入いただけます。他の金融機関さんも取り扱っていますが、特徴や取り扱う運用商品、加入時や毎月の口座管理等にかかる手数料などが異なりますので、まずはご相談ください。
ちなみに北海道信用金庫では、投資信託だけでなく、保険や預金も取り扱っていますので選択肢の幅は広くなっています。
パソコンやスマホから運用シミュレーションができるサイトがございますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
しんきん確定拠出年金インフォメーションサービス
http://www.wam.abic.co.jp/contents/C511000/401k/index.html
Q:iDeCo(イデコ)の最大の魅力とは何でしょうか?
やはり、税制優遇が受けられることが最大の魅力です。あとは、原則60歳までおろせないことでしょうか。おろせないことはiDeCo(イデコ)のデメリットであると言われていますが、お金はおろせると貯まらないものです。毎月の掛け金は少額でも、いつの間にか貯まっていて60歳の時に「やってて良かった!」と思っていただけるはずです。

Q:iDeCo(イデコ)ですと、アンケートで2番目に興味が高かった「病気や不時の災害への蓄え」に関しては対応できないですがどうしたらいいでしょうか?
医療保険や火災保険など、病気や災害に備える商品を取り揃えております。また、「蓄え」ということであれば預金の他に、「つみたてNISA(ニーサ)」という制度があります。積立預金の感覚で20年間非課税で運用できますし、積立時の手数料は無料、運用の手数料も他の投信と比較してかなり安くなっています。金融庁の基準をクリアした投資信託を毎月一定額積立するので、資産形成に適した運用方法といえます。また、iDeCo(イデコ)との一番の違いは資産の引き出しがいつでもできるので、いざという時に使えます。しかも掛け金は1,000円からなので気軽に始められます。
Q:ではiDeCo(イデコ)と、つみたてNISA(ニーサ)の両方で運用すると最強ですね!!
そうですね。入ってください、というよりは入った方がお客さまの将来のためになりますよ。と広くみなさんにお知らせしたいです。
インタビュー後記
運用というと何かギャンブル的に感じてしまう方が日本人は多いそうですが、選ぶ商品によっては長期間の運用に適したものもあるそうです。個々の性格に合った商品を選んで楽しく運用できそうですね。
北海道信用金庫さんは札幌信用金庫さん、北海信用金庫さん、小樽信用金庫さんが合併したことによって、より広い地域の方々に更に充実したサービスを提供できるようになったとのことです。
あなたの街の「しんきん北海道」に気軽に足を運んでみてはいかがでしょうか。
金庫情報:北海道信用金庫
略称:しんきん北海道
HP:http://www.shinkin.co.jp/hokkaido/
いよいよ暑くなってきました。来月7月は「暑さに関するお困りごと」についてエネモール会員のみなさんのお悩みやその工夫について特集していきます。お楽しみに!!
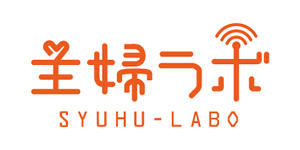
企画:主婦ラボ事務局
「主婦ラボ」は株式会社エルアイズが運営する北海道の女性の情報交換&モニターサイト。
商品や店舗のモニター会員募集中!
http://syuhu-labo.net